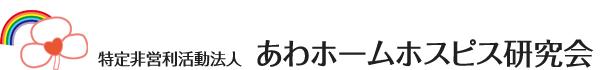病気でも障がいでも豊かに生きるために

特定非営利活動法人 あわホームホスピス研究会
理事長 五反田 千代
21世紀に入り、日本社会は、様々な天災人災に見舞われています。
『人のいのちの最期はいつでも訪れる』という現実を突きつけられているといえるでしょう。
日本の家族は1970年代より急激な経済成長を遂げ、ライフスタイルを欧米化、日本文化の家制度多世代同居を捨て核家族化の道を歩みました。家庭内で助け合い絆を深めあう日本人の特性があるにもかかわらず、心理的な距離ができました。
けがや病気がきっかけで他人の手を借りて生活するようになると、いろいろな苦痛が生まれます。(在宅ホスピス緩和ケアの理念では「全人的苦痛」と呼びます)
欧米では子供は独立して両親と別居することは当然で、要介護になると福祉施設で過ごすことがあたりまえの社会ですが、日本はそうではありません。基本血縁者が要介護の身内を面倒みるという社会通念の元様々な法制度がつくられています。
「家族に迷惑をかけたくない」という価値観も日本人特有のものといえます。
2015年の厚労省の終末期に関するアンケート調査結果がしめしたのは、自宅で最期まで過ごしたいと希望する人が60%、しかし実際に自宅で最期を迎えた人は、10%という事実です。
大規模な病院や施設に入ると、何十年も培った人間関係や慣れ親しんだ暮らしから切り離され、入居先のルールに合わせることになります。自宅で思い通りに「自分で考え、自分で決める」暮らしから「自分らしさ」を隠して生きる暮らしになります。介護保険制度は、介護度・健康状態によって入居できる施設がきまっており、状態が変わるたびに転所となり最期を迎えることになります。
生まれてくる場所や環境を選ぶことはできませんが、人生の終わりを自分で決めたいと思うのは無理なことでしょうか。介護保険制度創設20年の現在、人生を終える場所はさまざまな選択肢が用意されています。
わたくしは、2004年に宮崎県宮崎市で市民活動から芽生えた「ホームホスピス」という活動と出会いました。
5人の入居者が一軒のすまいで支え合い、ともに暮らす。24時間見守る介護スタッフと訪問診療医、訪問看護をはじめ、友人、ボランティアなどがチームとなってサポートします。ホームホスピスは、住人が自分で自分の一日を決め、持てる力を発揮し対等な人間関係をきずき、生きる張り合いを取り戻す場所です。そして、最後の瞬間まで普通に暮らし、ご家族や親しい人に囲まれて「逝く」というあたりまえを実現できる場所です。「終の棲家」の新たな選択肢として、人のいのちの尊厳を一番に考え本人の最善の暮らしを支えるホームホスピス活動は全国に広がりつつあります。
今、皆さん自身が「アフター要介護」をどのように暮らし最期を迎えたいのか、元気なときに考えその意思を周りに伝えていくことが求められています。
2024年7月1日
経歴
徳島県小松島市生まれ
取得資格・免許 看護師・保健師・助産師・精神保健福祉相談員・主任介護支援専門員
- 1982年
- 聖路加看護大学卒業(日野原重明学長(当時)に師事)
虎ノ門病院急性期病棟勤務(3年) - 1986年
- 東京都調布市役所勤務(26年)
- 2011年4月~2012年10月
- (有)白十字代表秋山正子氏より依頼を受け、東京都営戸山団地に「暮らしの保健室」を開設するため準備委員会メンバーとして従事
- 2011年8月~2012年3月
- 徳島県地域支え合い体制づくり事業「支え愛コーディネーター育成事業」に従事
- 2012年4月~2013年3月
- 小松島市介護福祉課 非常勤保健師勤務
- 2013年7月
- NPO法人あわホームホスピス研究会設立
★ボランティア活動★
- @ケアタウン小平デイサービス(東京都小平市2007~2011年)
- ◆小松島市社会福祉協議会 傾聴ボランティア (2012年~)
在宅ホスピス緩和ケア普及啓発活動
◇豊かに生きる講座◇
元気なときに「もしも自分自身で暮らせなくなったときどうするか」を考える機会を提供します。
「在宅医療」「ホスピス緩和ケアの理念の理解」「人が死に逝く過程」「病院と自宅をつなぐケアチームとは」「リビングウィルとエンディング」
ケアボランティアの育成と活動
がんを経験した人がほっとする場所~ピアプレイス暖での傾聴活動、「24時間見守りシェアハウス」でのボランティアをお願いしています。
◇カリキュラムの内容◇
- 当法人の理念とホスピス緩和ケアの概念
- ボランティアの責務とチーム活動
- 最期まで自宅で過ごす意味
- 介護、傾聴トレーニング
- 在宅医療を知る
医療・介護・福祉機関や地域住民ボランティアとの顔の見えるネットワーク作り
とくしまの医療福祉情報の提供
終の棲家の選択肢や在宅療養の暮らしに役立つ健康医療福祉の情報を集め、一般の方の目線で情報を検索できるように発信していきます。
デイホスピス ホームホスピス 2019年9月~「徳島とも暮らしの家ふくい」開設
市民ホスピス活動の拠点として、地域に開かれた地域住民の皆さんとの交流場所として運営しています
- 「家」の役割
-
- がん治療中の方の休息場所 徳島赤十字病院に徒歩5分の場所にあり、通院治療のハブとして利用できます。
- がんを経験した人がほっとする場所「ピアプレイス暖」を毎月第三土曜日に開催(秘密厳守)
がんという病気やがんを抱えて生きる方の理解・傾聴トレーニングなどを学んだボランティアが対応します。
手術や化学療法など受けながら暮らしていくには相当なエネルギーが必要です。主治医や身近な人には言えずにしまっていることをしがらみのない第三者に傾聴してもらうことで、張り切った心身が緩みます。そうすることで明日へ向かう原動力があなたの中に生まれます。 - ご近所交流
毎週木曜午後2~4時は「家」を開放しご近所の皆さんをお招きしています。ときには小松島市包括支援センター、生活支援コーディネーター、理学療法士などの関係機関と健康テーマを設け情報発信をしています。 - 「徳島とも暮らしの家ふくい」は民家を借り上げ、定員5名の方の生活をサポートしています。ヘルパーやボランティアが入居者と対等にかかわることで「生きる意欲」を取り戻していきます。最期の時まで、医師と訪問看護師など医療と連携しながら、ご本人らしく生ききることを支えます。